最近、目が疲れる。歳のせいかな?
と感じている40代のみなさん
諦めるのはまだまだ早いですよ。
その目の疲れ、実は照明環境のアンバランスが原因かもしれません。どんなに高性能なモニターを使っても、手元の明るさや光の色が合っていないと目は疲れるのです。
40代ともなると目の調整力(ピント調節機能)は低しています。「そんなことはない」と思いたい気持ちはわかります。が、若い頃よりも「光の質」に敏感になっているのは間違いない。
そこで今回は、目に優しいデスクライトの選び方とおすすめ機種を、在宅ワーク世代のあなたに向けて詳しく解説します。
なぜデスクライト選びが「目の疲れ」に直結するのか?
まずは目が疲れる原因についてみてみましょう。
明るさの差が“見えにくさ”と疲れを招く
人の目は「暗すぎる」「明るすぎる」「光のムラ」に弱いのです。
特に、モニターと手元の明るさに差があると、目がその都度ピントを調整しようとして疲れが蓄積してします。
「画面だけ明るく、周囲が暗い」という環境は要注意なのです。デスクライトで明るさを均一に保つことが、疲れ目対策の第一歩です。
40代からは“ピント調整力”の衰えが顕著に
加齢によって毛様体筋が硬くなり、近くと遠くのピント切り替えが難しくなるといわれています。
そのため、少しの明暗差でも負担が増え、目の疲れや焦点のぼやけを感じやすくなります。
つまり、40代以降は「光の質」そのものを整えることが、生産性と健康を守るカギなのです。
目に優しいデスクライトの選び方6つのポイント
つづいて選び方をみてみましょう。
① フリッカーフリー(ちらつきなし)
安価なLEDライトには、肉眼では見えない“ちらつき”があるのをご存知ですか?
これが長時間続くと、無意識のうちに目や脳にストレスを与えます。ここは「フリッカーフリー対応」の製品を選びましょう。
② 色温度を調整できる(昼白色〜電球色)
作業効率を上げたい昼は「昼白色」、リラックスしたい夜は「電球色」。
シーンに合わせて光の色を変えられる調色機能付きデスクライトがおすすめです。
③ 明るさを無段階で調整できる
仕事内容や時間帯によって必要な明るさは変わるのです。
無段階調光タイプなら、眩しすぎず暗すぎない最適な光を保つことができて便利です。
④ 高演色性(Ra値80以上)
演色性とは、光が色を自然に見せる力。
Ra値80以上なら資料や書類の色が正確に見え、目も疲れにくくなります。
⑤ デスク環境に合った照射範囲
モニターが2台ある場合は、広範囲を均一に照らせるライトを選ぶのがカギ。
逆に、書き作業中心なら、狭めで集中的に照らすタイプが便利です。
⑥ 設置位置と角度にも注意
ライトは利き手の反対側に置き、影ができにくいよう角度を調整しましょう。
光が直接目に入らない位置が理想です。
用途別おすすめライト診断
| 作業スタイル | おすすめタイプ | 特徴 |
|---|---|---|
| PC作業中心 | 広範囲照射+自動調光型 | モニターとの明るさバランスを保つ |
| 書類・読書中心 | 暖色系の柔らかい光 | 目に優しく落ち着ける |
| デザイン・資料チェック | 高演色性(Ra90以上) | 色の誤認を防ぐ |
| コスパ重視 | シンプル機能+フリッカーフリー | 5,000円前後で快適に使える |
おすすめデスクライト7選
BenQ MindDuo
プロ仕様の自動調光モデル。
Ra95の高演色性で、長時間PC作業でも疲れにくい。
在宅ワーカーの定番人気です。
BenQ ScreenBar Halo
モニター上に取り付けるバータイプ。
省スペースながらフリッカーフリー対応。
映り込みを防ぐ設計で目に優しい。
GENTOS DK-R115BK
コスパ最強のベーシックモデル。
調光・調色付きで読書や書類作業にぴったり。
アイリスオーヤマ LDL-TM8N
無段階調光・調色対応。
デザインもシンプルで自宅オフィスに馴染みやすい。
山田照明 Z-10N II
可動アームで照射範囲を自在に調整可能。
長年の人気シリーズで信頼性抜群。
無印良品 LEDデスクライト(調光式)
ミニマルデザインで部屋に溶け込む。
自然な光で、読書にもPC作業にも◎。
GENTOS DK-R255BK
広範囲を明るく照らせるアーム型。
デュアルモニター派におすすめです。
目に優しく使う5つのコツ
- ライトは利き手の反対側に置く
- モニターと手元の明るさをそろえる
- 朝昼は白っぽく、夜は暖色に切り替える
- 光が直接目に入らない角度を意識する
- LEDも劣化するので、数年ごとに見直す
少しの工夫で、目の疲れは大きく減らせます。
まとめ|デスクライトは“仕事の質”を上げる自己投資
目の疲れは、努力の問題ではなく「環境の問題」です。40代のあなたに必要なのは、自分の目をいたわる光。
快適なワークスペースづくりは、未来の自分への投資ですよ。
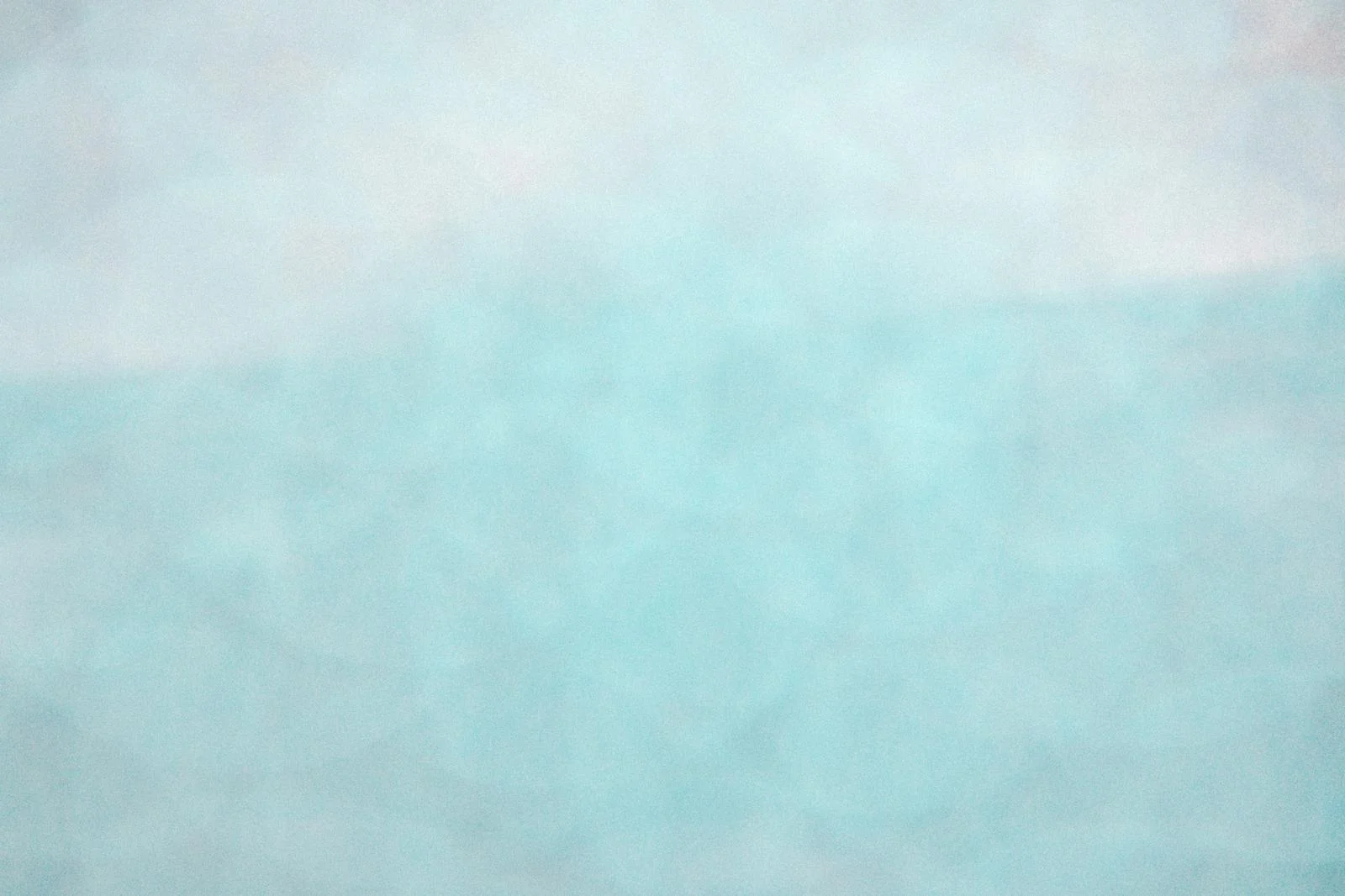

コメント